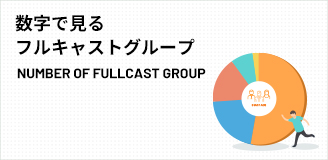人材派遣の契約内容とは?企業が扱う書類や派遣社員の受け入れの注意点を解説

派遣労働者を受け入れる場合に気になるのが契約書です。
派遣社員に対して結ぶ契約書のことを派遣雇用契約書と呼びますが、派遣先と派遣労働者の間で取り交わす必要はありません。
一方で、派遣先企業は派遣元企業との間で契約を結びます。契約内容は多岐に渡っており、複数の書類を作成するため、確認すべきポイントが多いので注意しましょう。
この記事では、派遣先企業が派遣会社とやり取りする書類と提携の流れ、派遣社員を受け入れる際の注意点について解説します。
目次
- 基本契約書
- 個別契約書
- 抵触日の通知書
- 待遇等に関する情報提供の書類
- 事業所単位・個人単位の期間制限を守ること
- 就業前に派遣先が直接面接をおこなうことの禁止
- 適切な派遣契約の締結
- 離職後1年以内の労働者受け入れ禁止
- 派遣元によって社会保険に加入されているかの確認
- 派遣労働者からの苦情処理に関する処理体制の整備
- たとえば、派遣先・派遣元企業間での連絡協議会の設置や、派遣労働者からの提案を受け入れる体制などを構築しましょう。
- 派遣先責任者の選任
- 派遣先管理台帳の作成
- 労働者の募集情報の提供
- 派遣労働者と社員の待遇の均衡化
- 派遣先は雇用契約書を発行しない?
- 派遣契約の書類は誰がつくる?
- 作成した書類に期限はある?
派遣は派遣先と労働者の雇用契約ではない

派遣労働者を受け入れる時に結ぶ契約書ですが、派遣先と労働者の間での雇用契約はありません。契約を結ぶのは人材派遣会社と労働者であり、この両者の間で取り交わされるのが派遣雇用契約書です。
また人材派遣会社は、賃金や契約期間、就業時間や派遣先となる事業所の場所などが記載された労働条件通知書によって労働者に契約内容を通知します。これは労働基準法にて通知が義務付けられている書類です。
また、労働条件通知書と似たものに就業条件明示書というものがあります。労働条件通知書は労働基準法、就業条件明示書は労働派遣法に基づいて作成する書類のため、それぞれ別々に書類を作成する必要がありますが、同じ項目が多いため「就業条件明示書兼労働条件通知書」として交付する人材派遣会社もあります。
派遣先企業が人材派遣会社とやりとりする書類

派遣先が派遣会社とやりとりする書類は以下の4つです。
- 基本契約書
- 個別契約書
- 抵触日の通知書
- 待遇等に関する情報提供の書類
書類の内容を、詳しく見てみましょう。
基本契約書
基本契約書の正式名称は、労働者派遣基本契約書といいます。派遣元と派遣先の間で取り交わす書面であり、継続的に派遣労働者を派遣することが定められています。作成は義務ではありませんが、トラブル回避のためのお守りとして作成することが多いようです。
記載項目の一例は以下のとおりです。
| 記載項目 | 記載内容 |
| 目的 | 派遣元が派遣先に、どんなスキルを持った労働者を派遣するかといった、契約のおもな目的を明記する |
| 適用範囲 | どのような条件や状況かで本契約が適用されるかを明記する。おもに派遣される労働者の職種や業務内容など |
| 個別契約 | 継続的な派遣の枠組みの中で、具体的な派遣の条件や期間を定める個別の契約について明記する |
| 派遣料金 | 派遣元が派遣先から受け取る派遣料金の計算方法や支払い条件を明記する |
| 派遣先責任者・派遣元責任者 | 派遣元、派遣先企業での本契約に関する責任者を明記する。労働者との窓口になることが多い |
| 指揮命令者 | 派遣先で派遣労働者に対する具体的な業務指示を出す人物を明記する |
| 適正な就業条件の確保 | 派遣労働者に対して、労働時間や休憩、休日などで適正な労働条件を提供すると明記する |
| 適正な労働者の派遣義務 | 派遣元は、要求されたスキルや経験を持つ適切な労働者を派遣する義務があると明記する |
| 代替要員の確保 | 派遣労働者が病気等で働けなくなった場合に、代わりの人材を提供することに関する項目を明記する |
| 苦情処理 | 派遣労働者や派遣先からの苦情に対する処理方法を明記する |
| 派遣労働者の個人情報の保護 | 派遣労働者の個人情報を保護するための措置を明記する |
| 企業秘密および個人情報の守秘義務 | 派遣労働者が業務上知り得た企業秘密や個人情報を外部に漏らさないことに関する義務を明記する |
| 安全衛生 | 派遣先での安全な労働環境の提供に関する項目。 おもに作業場の安全基準や健康管理に関する方針を明記する |
| 福利厚生施設の利用 | 派遣労働者が派遣先の食堂や健康診断などの福利厚生施設を利用できるか明記する |
| 損害賠償 | 契約違反が発生した場合の損害賠償に関する規定を明記する |
| 契約解除 | 契約を解除できる状況や手続きに関して明記する |
| 有効期間 | 契約が有効な期間を明記する。具体的な日時を盛り込む
|
| 解除制限 | 契約解除にあたっての条件や制限を明記する |
| 協議 | 契約に関する疑問や未定義の事項は、双方が協議すると明記する |
| 管轄裁判所 | 契約に関する紛争が生じた場合に管轄する裁判所を明記する |
上記はあくまでも一例で、契約する企業や内容によっては足す必要があると覚えておきましょう。
個別契約書
労働者派遣個別契約書では、おもに派遣社員の保護に関する規定が盛り込まれます。基本契約書とは異なり法律で作成が義務付けられており、派遣労働者を受け入れる場合は必ず作成しなければなりません。
記載する項目の一例は次のとおりです。
| 記載項目 | 記載内容 |
| 業務内容 | 労働者が担う責任の重さや範囲を明記する。たとえば、プロジェクトのリーダーや一般メンバーなどの役職を明記する |
| 業務にともなう責任の程度 | どのような条件や状況かで本契約が適用されるかを明記する。おもに派遣される労働者の職種や業務内容など |
| 就業場所 | 労働者が働く具体的な場所を明記する |
| 組織単位 | 派遣労働者が所属する部署やチームを明記する |
| 指揮命令者 | 派遣労働者に対して直接業務指示を出す人物を明記する |
| 派遣期間 | 派遣労働の開始日と終了日を具体的に明記する |
| 就業日・就業時間・休憩時間 | 週何日働くか、1日の労働時間、休憩時間の長さなどを具体的に明記する |
| 安全および衛生 | 労働者が安全かつ健康に働けるようにするための措置を明記する |
| 派遣労働者からの苦情の処理 | 労働者が苦情を提出した際の対応方法を明記する |
| 労働者派遣契約の解除にあたって発生する派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 | 契約終了時の雇用継続のための方策を明記する |
| 派遣元責任者・派遣先責任者 | 派遣元と派遣先の本契約における代表者を明記する |
| 就業日外労働・時間外労働 | 通常の勤務時間や勤務日以外の労働についての取り決めを明記する |
| 派遣人員 | 派遣される労働者の人数を明記する |
| 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与 | 労働者の福祉を高めるためのサービスや制度を明記する |
| 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 派遣労働者を直接雇用に切り替える際のトラブルを避けるための方法を明記する |
| 派遣労働者を無期雇用派遣労働者または60歳以上の者に限定するかどうか | 特定の条件を満たす労働者のみを派遣するかの決定を明記する |
| 労使協定方式の対象となる派遣労働者に限定するかどうか | 労使間で特別な協定を結んだ労働者のみを対象にするかどうかを明記する |
| 紹介予定派遣に関する事項 | 派遣先企業への直接雇用を前提とした派遣形態に関する取り決めを明記する |
なお、書式は厚生労働省「労働者派遣(個別)契約書 記入例」にて公開されています。
抵触日の通知書
抵触日とは、労働者派遣法において定められた3年の年限を過ぎた翌日のことを指します。事業所単位と個人単位の2種類がありますが、どちらも3年の上限がついています。
この書類は派遣先から派遣元に対し、事業所単位の期間制限の抵触日を記載して提出しなければなりません。記載内容は以下のとおりです。
- 派遣元企業の事業所名・代表者名
- 派遣先企業の所在地・事業所名・代表者名
- 派遣受入事業所の所在地・事業所名
- 派遣可能期間の抵触日
こちらの書式は厚生労働省「抵触日通知書例」で公開されているため、必ず提出するようにしてください。
待遇等に関する情報提供の書類
待遇面などに関する情報共有ができる書類も作成しなければなりません。義務ではありませんが、基本契約書や雇用契約書と同様、トラブルを回避する目的で作成されます。派遣労働者がどのような待遇で受け入れられているのかなどを明記しておくことで、トラブルを未然に回避できるでしょう。
派遣契約を締結する流れ

派遣契約を締結するまでの流れは「労働者派遣契約」によると以下のとおりとなっています。
- 基本契約を締結する 派遣元と派遣先企業の間で、継続的に取引をするうえでの共通事項を締結する
- 事業所抵触日の通知 派遣先からの依頼を受けると同時に、派遣先から派遣元に対して事業所抵触日の通知を送る
- 個別契約の締結 派遣先と派遣元の間で、業務内容や派遣先、その他就労条件をすり合わせ合意を得られた時点で締結
ここまでの書類のやり取りをして、晴れて派遣労働者が派遣先に送られます。通知関係の書類に関しては記載事項が少ないものの、契約関係や就労条件の書類は記載事項が多いのが特徴です。すべての書類においていえることですが、抜けや漏れがないようしっかりと作り込みましょう。
ゼロから作るのは労力がかかるため、公開されているテンプレートを使用しながら必要事項を記入しても良いかもしれません。
企業が派遣社員を募集してから採用するまでの流れを詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
派遣社員を受け入れる際の注意点

派遣社員を受け入れる際には、いくつかの注意点があります。厚生労働省が発行している「派遣社員を受け入れるときのおもなポイント」では、以下の項目に注意するよう呼びかけられています。
- 事業所単位・個人単位の期間制限を守ること
- 就業前に派遣先が直接面接をおこなうことの禁止
- 適切な派遣契約の締結
- 離職後1年以内の労働者受け入れ禁止
- 派遣元によって社会保険に加入されているかの確認
- 派遣労働者からの苦情処理に関する処理体制の整備
- 派遣先責任者の選任
- 派遣先管理台帳の作成
- 労働者の募集情報の提供
- 派遣労働者と社員の待遇の均衡化
法的に守らなければならない内容から、派遣先企業に努力義務として求められる内容までさまざまです。
上記の内容は派遣労働者を守るために必要なことであり、違反すると法的に罰せられる可能性もあるため、受け入れる前に構築しておく必要があるでしょう。
派遣社員を受け入れる際の注意点を順番に解説します。
事業所単位・個人単位の期間制限を守ること
労働者の派遣では事業者単位と個人単位で期間制限があります。
原則、同一の事業者に対して派遣できる期間は3年が限度です。派遣先が3年を超えて派遣を受け入れたい場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合や事務所の労働者の過半数を代表する者などからの意見を聞く必要があります。
また、同一の派遣労働者を、同じ派遣先の同じ課に派遣できる期間も3年が限度です。
つまり、ある派遣労働者を受け入れた場合、3年ごとに事業所の過半数労働組合や事務所の労働者の過半数を代表する者などからの意見を聞き、了承された場合でも、該当の派遣労働者は別の課に異動してもらう必要があります。
同じ派遣労働者を3年以上、同じ課で働かせることはできないと覚えておきましょう。
就業前に派遣先が直接面接をおこなうことの禁止
原則、派遣先企業は派遣労働者の指名や、派遣就業の開始前の面接、 履歴書を送付させるなどはできません。
なお、紹介予定派遣の場合は例外です。
適切な派遣契約の締結
派遣労働者を受け入れる派遣先企業は次の適切な派遣契約の締結を求められます。
- 港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関連業務(紹介予定派遣等の場合は例外)への派遣は禁止
- 派遣契約を締結する前に、派遣元事業主に対して、事業所単位の期間制限の抵触日の通知をおこなう
- 派遣契約では、業務内容などのほかに、派遣先の都合による派遣契約の中途解除の際に、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項(派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用の負担に関することなど)についても定めることが必要
適切な派遣契約の締結がされているか、確認しましょう。
離職後1年以内の労働者受け入れ禁止
原則、自社で直接雇用していた社員やアルバイトなどを、離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることはできません。
なお、60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されます。
派遣元によって社会保険に加入されているかの確認
派遣先企業は、派遣元企業が派遣労働者への社会・労働保険の加入が適切に行われているか確認する必要があります。
派遣元企業に対して健康保険証や雇用保険被保険者証などのコピーの提出を求めましょう。
派遣労働者からの苦情処理に関する処理体制の整備
派遣先企業は、派遣労働者を受け入れる際に苦情の処理体制を整備する必要があります。
たとえば、派遣先・派遣元企業間での連絡協議会の設置や、派遣労働者からの提案を受け入れる体制などを構築しましょう。
派遣先責任者の選任
派遣先企業は派遣先責任者を選任する必要があります。
派遣先責任者とは、派遣契約の派遣先企業側の責任者で、派遣先管理台帳の作成や派遣労働者からの苦情処理、派遣元企業との窓口などを担当する役割です。
派遣先管理台帳の作成
派遣先責任者が作成する派遣先管理台帳とは、派遣労働者の労働日や労働時間などを記録した台帳です。派遣会社への業務報告にも使用されるため、忘れずに作成しましょう。
労働者の募集情報の提供
派遣先企業は正社員を募集している場合、事業所で継続して1年以上受け入れている派遣労働者に募集情報を提供する義務があります。
また、同じ課で3年間受け入れる見込みがある派遣労働者の直接雇用を派遣元企業から受けて、正社員やアルバイトなどを募集している場合も、派遣労働者に募集場を提供する義務があるため、忘れずに対応しましょう。
派遣労働者と社員の待遇の均衡化
派遣労働者を受け入れる場合、派遣先企業は同種の業務に従事する労働者との待遇の均衡を図る必要があります。
たとえば、労働者に業務に必要な教育訓練を実施するなら派遣労働者にも同じ訓練を提供する、労働者が福利厚生施設を利用するなら派遣労働者にも同じ福利厚生施設を利用する機会を与えるなどの配慮をしましょう。
派遣契約の書類に関するよくある質問

派遣契約の書類に関するよくある質問を順番に解説します。
派遣先は雇用契約書を発行しない?
雇用契約書は派遣元と派遣労働者の間で取り交わされているため、派遣先は雇用契約書を発行しません。その代わりに派遣元から労働条件通知書が派遣労働者に渡され、受領をもって派遣先との雇用契約締結となります。
派遣契約の書類は誰がつくる?
派遣契約の書類は派遣元が作成する「基本契約書」「個別契約書」の2種類と、派遣先が作成する「抵触日の通知書」とそれに付随する待遇などの情報を記した書類に分かれます。
作成した書類に期限はある?
法令上は、派遣契約に関する書類に保存期間はありません。ただし、派遣労働者を管理するための派遣元管理台帳と呼ばれる書類に関しては派遣就業が終了した日から3年間の保管が義務付けられているため、個別契約書などの関連書類においても同様に保管しておくことが望ましいです。
まとめ
労働者派遣に関する契約書が非常に特殊で、慣れていなければ手続きが複雑で難解に感じてしまうでしょう。
また、派遣社員を受け入れる場合は期間制限や適切な派遣契約の締結などが求められるため、内容を精査する必要もあります。
しかし、ひとつずつクリアすることで、大きなトラブルやミスにつながるリスクは低くなります。法律で義務付けられているという理由もありますが、派遣労働者を守るためにもしっかりとした契約書を作成してください。
人材をお探しの企業様はこちら
1990年の設立以来、
業界をリードする実力をぜひご活用ください。
企業のご担当者専用ダイヤル